| 長谷川利行という画家の生き方 | 随筆のページへ トップページへ File No.160219 |
|
 |
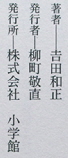 |
BSテレビの231chで「放送大学」の過去の講座が放映されている。過日「日本美術史」という講座があり、「大正・昭和期」の回で長谷川利行(1891〜1940)という画家を解説していた。その解説の内容から、作品はもちろんだが、その生き方・人生にも興味を持ち、吉田和正著「アウトローと呼ばれた画家---評伝・長谷川利行」(小学館)を読んでみた。この画家の壮絶な人生がすごい。画家として活躍したのは、わずか10数年だったが、その短い時間を嵐のように駆け抜けた。天才的でマルチな才能を持ちながら、生存中に名声を得ることはなかった。京都に生まれ29歳で上京するまでは、親がかりで金銭面の苦労はなく、「木葦(もくい)集」という歌集を自費出版するほど文芸に秀でていた。彼の短歌について「評伝・長谷川利行」にはこう書いてあった。『利行の短歌は繊細で澄んだ心の動きを抒情的に調べ高く詠いあげた・・・』。ところが、何の不自由もなく恵まれていたはずのこの時期に、彼のその後の人生を予感させるような短歌を詠んでいる。 |
| 「評伝 長谷川利行」 | ||
| "人知れずくちも果つべき身一つの今かいとほし涙拭はず" | ||
| "魂にとぢこもりつゝ落涙す松山の庭鴉啼き過ぐ" | ||
| 京都の時代と、上京してからの暮らしの落差が余りに激しい。東京では絵画一筋に生き、帝展や二科展などに出品し、入選もし樗牛(ちょぎゅう)賞なども受けている。しかし、望んでいた二科会会員に推挙されることはついになかった。それは長谷川の生き方に起因していた。天才的な才能、強烈な個性であるが故に、長谷川にとっては生きづらい世の中だった。いつの世も、世渡りの下手なものにとって世間は冷たい。ドヤ街や木賃宿をねぐらにしていた長谷川は、朝、宿を追い出されると一日中歩き回り絵を描いた。その格好は、まるでルンペンだったという。命を繋ぐために、描いた絵を五十銭、一円で叩き売った。その日を生きる糧を得るため、なりふり構わず絵を押し売りもした。貧困と安酒と流浪は、次第に彼の体をむしばむ。ついに彼は行き倒れとなり、養育院へ収容される。最期はベッドから転げ落ちた状態で、誰からも見取られることなく、孤独に人生を終えている。しかし、彼の画人としての誇りと気迫は、最後まで衰えることはなかった。「手術はいやだ、そんなものはやらない。点滴も注射もやりたくない。おれは絵を描くんだ」。 |
 「自画像」 |
 「タンク街道」 |
長谷川は、大正12年の関東大震災後の復興していく東京を描いて回った。「タンク街道」を描いたときの長谷川の様子を、美術史の講座ではこう紹介していた。『利行は路傍にイーゼルを立て、台風のような凄まじさで、チューブのまま絵の具をギュッギュッとなすりつけ、ナイフで削り"ウォッ ウォッ"と吠えながら描き続けた』。持てる全神経を集中させ、吠えながら一気に描き上げる。そんな長谷川の魂から生み出される作品は、気迫に満ちたフォービスム的な絵だった。その色彩感覚は、京都時代に描いた水彩画とは正反対だったようだ。京都時代には「自然の色彩と相違のない色を出して見せる」と言っていたという。彼の色彩感覚を激変させたものは何だったのか。それは彼が生きている環境ではなかったろうか。関東大震災から立ち上がっていく街や庶民のエネルギーに触発され、それを激しい色彩で荒々しく表現しようとしたに違いない。長谷川の作品の中でも「ノアノアの女」がいい。展覧会締切当日、一時間半で描き上げたものだという。本脳に突き動かされた色が、激しくキャンバスに叩きつけられている。これこそが長谷川の芸術ではなかろうか。 |
| 長谷川は問う。『絵を描くことは、生きることに値すると云ふ人は多いが、生きることは絵を描くことに価するか』。画家として根源的な問いかけである。彼は晩年ドイツの哲学者・ニーチェの本を愛読していた。彼が最期を迎えた部屋にはこの本が残されていた。ニーチェは、「永劫回帰」という考えを説いた。今の人生がどんなに悲惨なものであれ、永遠に繰り返されていく。それをありのまま引き受け、人生を肯定することで人間を超えた「超人」になれる。さらにニーチェは生命のすべてが持つ「力への意志」を積極的な概念としてとらえ、それはニヒリズムを克服し、自分なりの価値観をつくり、より高い可能性へと向かわせる。「力への意志」こそ、生存の本質なのである。おそらく長谷川は、ニーチェにそんなことを学んだに違いない。人間が生きる意義とは、生きるに値する生き方を構築し、それを生き抜くということだろう。長谷川が自らに問うた"絵を描くことは、生きることに価するか"は、命を削りながら、魂の叫びで描くほどの覚悟がいる。そうあってはじめて"描くこと"が"生きる"ことに対峙できる。彼は画人として、その問いに自らを投げ入れ、激しく、凄まじい人生を構築し、それを生き抜き、嵐のように駆け抜けていった。 |
 「ノアノアの女」 |
| 随筆のページへ | トップページへ |